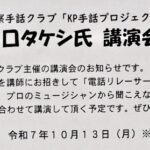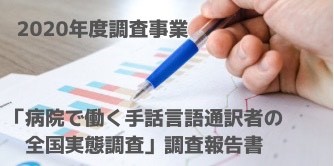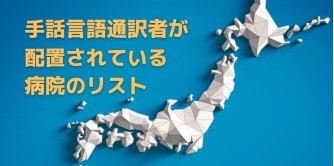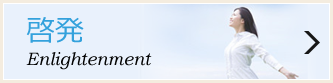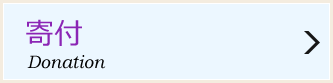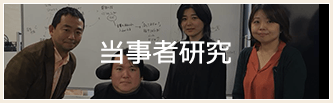【ご報告】 東京都障害者IT地域支援センター主催 東京都指定事業講習会『聞くことの困難を支援する』(2025/7/1, 7/3)
2025年7月1日(火)、3日(木)の2日間、東京都障害者IT地域支援センター様からのご依頼で、デジタル技術活用支援者養成講習会『聞くことの困難を支援する』が行われ、1日目(7/1)を理事の山口タケシが、2日目(7/3)を理事長の伊藤芳浩が講師を担当しました。
なお、本講習会は東京都が指定する事業の一つとして行われたもので、参加対象となる障害者のデジタル技術支援関連を担当する都内の区市町村の職員および関連支援施設・機関の従事者など両日とも8名ずつが参加されました。
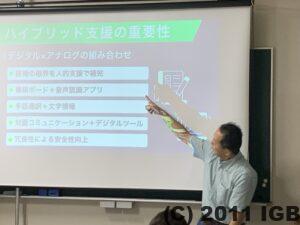
講演の様子:伊藤理事長(1)
今回の講習会は両日とも約4時間という枠の中、聴覚障害者への効果的な支援について、デジタル技術の活用や知識にとどまらず、当事者の気持ち(心理面)や実際の困りごと(実情)についても深く理解していただけるよう以下のようなセクションに分けてお伝えするとともに、聴覚障害当事者の置かれている状況(の一部)を受講者に体験していただくようなワークショップも盛り込んで行われました。
- 当事者視点から考える聴覚障害と支援
- デジタル支援の可能性と限界
- 災害時の情報支援を考える
- 実践ワークショップ「当事者体験と支援実践」
- 講演の様子:伊藤理事長(2)
- 講演の様子:山口理事
参加者からの声
後日、参加者から以下のような感想が寄せられ、本講習会が大変有意義なものであったことがうかがえました。(※カッコ内は筆者による注釈)
- 情報保障に関して「質・量・時間」の3要素が障害の有無にかかわらず等しく担保されるべきであるという視点は、多くの人に伝わりやすい明快なメッセージとして印象に残りました。
- デジタルとアナログの両面から支援を行う“ハイブリッドな支援”の必要性や、災害時など緊急時における情報保障の課題については、支援に関わるすべての人に広く共有し、備えていくことが重要であると感じました。
- 聴覚障害のある方を「全ろう」「難聴」などと分類し、支援方法を一方的に決めてしまう傾向がありましたが、実際には「どう生きたいか」「どのようにコミュニケーションを取りたいか」を決める主体は当事者自身であるという視点を改めて理解しました。
- 聴覚障害者の方々が情報弱者とならないよう、「同じ情報を同じタイミングで」「正確に伝わっているか」を常に確認し続ける姿勢が重要であるという言葉はとても印象に残っています。
- 会議で1番不安なのは「誰が話してるかわからない事」というのが驚きだった。(発言者の名前が表示されない音声認識字幕を使った会議の事例紹介の流れを受けて)
- 当事者の立場に立って接することのできる支援者になりたいと強く感じました。また、手話通訳の素晴らしさを間近で体験し自分も習得してみたいと思いました。
- 当事者の声、意見意思を聞く機会を設けること、その姿勢を大事にし支援に活かしていきたい。
- 素晴らしいご講演をいただき、誠にありがとうございました。「心揺さぶられる」とはこういうことを言うのだと、強く感じています。(自身が全盲のボランティアの方より)
- 「ろう者は聞くこと以外は何でもできる!」 この力強い言葉は、励みになりました。(自身が聴覚障害の方より)
なお、『この講座は今後の業務に有用であると思いますか?』 というアンケートの設問に対し、アンケート回答者の全員が 『はい』 を選択していました。
今後の展望
今回の講習会は、障害者への支援を担当する職員・関係者を対象に行われたものですが、担当者がしっかりと理解・認識することはもちろんのこと、そこから派生して障害者支援という領域にかかわらない多くの方にも理解が広まることを願っています。
NPO法人インフォメーションギャップバスターとしては、今後もこうした機会を通じて、障害の有無にかかわらず誰でも等しく情報を得ることができ、誰もが安全で安心して暮らせる社会を目指して活動を続けていきたいと考えております。
(文責:山口タケシ NPOインフォメーションギャップバスター理事)