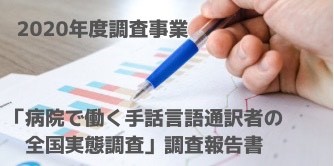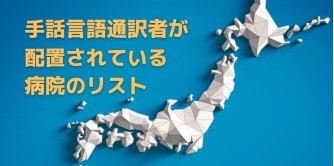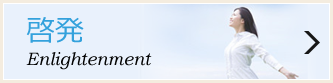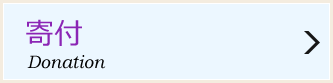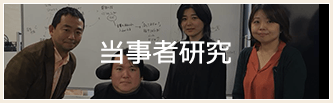理事長インタビュー
 NPOインフォメーションギャップバスター理事長 伊藤 芳浩さんに、設立の経緯や団体の目指すものなど熱い想いを語っていただきました。
NPOインフォメーションギャップバスター理事長 伊藤 芳浩さんに、設立の経緯や団体の目指すものなど熱い想いを語っていただきました。
Q1. NPOインフォメーションギャップバスターはどのような経緯で設立したのでしょうか?
私が勤めている一般企業では、周りの方々が聴覚障がいへの理解を示してくださり、多大なエンパワーメント(※1)がなされていました。特に、耳が聞こえないことで情報量に差が出ないよう、会議では事前に資料を共有してくださったり、チャットツールを活用したコミュニケーションを工夫してくださったりと、さまざまな配慮をしていただきました。そのおかげで、聞こえる方と遜色なく働くことができています。
一方で、同じように聴覚障がいがありながら、コミュニケーションがうまくいかず十分な情報が得られない方も多くいらっしゃいます。実際、コミュニケーションバリアがある方の転職・離職率が高いのも事実です。「この状況を何とか変えたい」という強い想いがありました。
そこで、同じような志を持つ仲間たちと話し合いを重ね、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支え合う「コミュニケーションバリアフリー」を推進することで、誰もが暮らしやすい豊かなコミュニケーション社会の実現を目指すNPOを設立しました。
※1:コミュニティメンバーが自分の力を十分に発揮できるように権限を与えたり、任せたりすること
Q2. NPOインフォメーションギャップバスターは誰のための団体なのでしょうか?
実は、すべての市民のための団体だと考えています。「えっ、障がいのある人だけじゃないの?」と思われるかもしれませんね。でも、立場や環境が変われば、誰でもコミュニケーションに困難を覚える可能性があるんです。
例えば、海外旅行に行って現地の言葉がわからないとき、道を尋ねたり、レストランでメニューを注文したりするのに苦労した経験はありませんか? あるいは、専門用語が飛び交う会議で置いてけぼりになった経験は? これらも広い意味でのコミュニケーションバリアです。
特に、日常生活では音声コミュニケーションが中心のため、耳が聞こえないとかなり不便を感じます。そういった意味で、聴覚障がい者の多くは日頃からコミュニケーションのしづらさに悩んでいる関係で、当事者(※2)意識が比較的高いと思います。そのため、会員の多くは聴覚障がい者が占めていますが、コミュニケーションのしづらさは視覚障がい者、発達障がい者、外国にルーツを持つ方など、あらゆる方に起こりうると考えています。
※2:起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のこと
Q3.コミュニケーションしづらさとはどのようなことでしょうか?
聴覚障がいや言語障がい、あるいは使用言語の違いなどの理由によって、人と人のやり取りが十分にうまくいかないことが日常的に起こっています。意思疎通がうまくいかないことで孤立したり、必要な情報が得られず不利な状況に陥ったりすることがあるんです。
具体的な例を挙げると、電話ができないためにリアルタイムなコミュニケーションが難しく、職場で「電話対応ができる人」という理由だけで活躍の場が限定されてしまうことがあります。これが経済格差につながります。また、生活面でのストレスが積み重なったり、医療機関で医師や看護師との会話が十分にできなかったりすることで、健康格差も生じてしまいます。
このように、コミュニケーションのしづらさは、生活のあらゆる面に負の影響をもたらしているんです。
Q4.コミュニケーションしづらさはなくした方がよいのでしょうか?
ぜひなくしていきたいと考えています。コミュニケーションのしづらさは一次的な問題に見えますが、その先には大きな二次的影響があるんです。
たとえば、情報が十分に得られないことで昇格の機会を逃したり、割引情報やお得なサービスを知らずに経済的な負担が増えたりといった経済格差。また、医療情報が十分に得られなかったり、医療従事者とのコミュニケーションが不十分だったりすることによる健康格差。これらが積み重なって、大きな格差につながっていきます。
逆に言えば、コミュニケーションのしづらさをなくすことで、当事者の生産性が向上し、給料アップや税収増加にもつながります。つまり、本人だけでなく社会全体にとってもプラスになると考えています。
Q5.「コミュニケーションバリアフリー」とはどういう意味なのでしょうか?
コミュニケーションのしづらさには、大きく二つの要因があると考えています。一つは障がいや能力といった個人的要因。もう一つは、理解不足・差別・排除による心のバリアといった社会的要因です。
「コミュニケーションバリアフリー」とは、これらの要因をお互いのメリットを増やす方向で相互理解を深めることで、コミュニケーションのしづらさをなくしていった状態を指します。単に「バリアを取り除く」だけでなく、「お互いが理解し合い、支え合う」という相互性が重要なポイントです。
Q6.社会に期待することは何でしょうか?
様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が相互に理解を深めて支え合う「コミュニケーションバリアフリー」が広がることで、誰もが暮らしやすい豊かなコミュニケーション社会になることを期待しています。
「障がいのある人を助ける」という一方向的な関係ではなく、互いに学び合い、支え合う関係性が築かれていく。そんな社会を目指しています。
Q7.「コミュニケーションバリアフリー」のためにどんなことをしていますか?
主に三つの柱で活動しています。
まず、「啓発活動」として、「コミュニケーションバリア」の問題を社会に広く知ってもらう取り組みを行っています。相互理解を深め合い、共生社会を創り出していくことを目指しています。
次に、「要望活動」として、政府や関連団体へ「コミュニケーションバリア」問題の改善要望を提出しています。制度や仕組みを変えることで、コミュニケーションしやすい豊かな社会を創り出していきたいと考えています。
そして、「自立支援」活動として、コミュニケーションに困難を覚える当事者自身が自分の困りごとなどを言語化する取り組みを行っています。これが相互理解や支援のきっかけづくりにつながっています。
Q8.今後の目標を教えてください
当NPOメンバーの大部分は会社員ということもあって、職場におけるコミュニケーションバリアには特に大きな関心を持っています。そのため、現在は労働分野を重点的に取り組んでいますが、最終的にはすべての分野において、コミュニケーションバリアのない社会を目指していきたいと考えています。
教育、医療、行政サービス、防災など、生活のあらゆる場面でコミュニケーションバリアフリーが実現される。そんな未来を、仲間たちと一緒に創っていきたいですね。
– 色々と取り組んでいるのですね!今日は色々とお答えいただき、ありがとうございました。