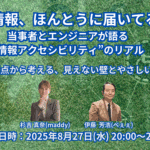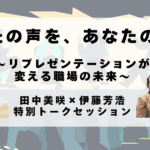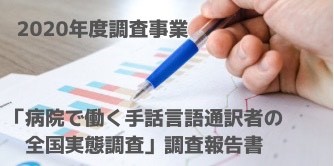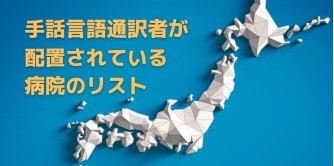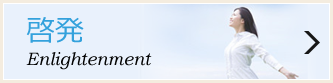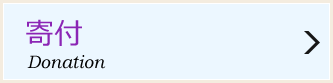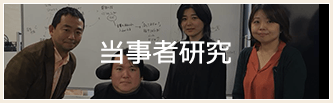【ご報告】トークイベント「その情報、ほんとうに届いてる?──当事者とエンジニアが語る“情報アクセシビリティ”のリアル」
2025年8月27日(水)、オンラインで開催されたトークイベント「その情報、ほんとうに届いてる?──当事者とエンジニアが語る“情報アクセシビリティ”のリアル」。
登壇者は、フロントエンドエンジニアでアクセシビリティの第一線で活躍する杉吉真奈(maddy)さんと、日本手話を第一言語とするろう者でNPO法人インフォメーションギャップバスター理事長の伊藤芳浩(べぇぇ)さん。
参加者は約120名(アーカイブ視聴を含む)。行政や教育、エンジニア、デザイナー、学生など幅広い分野から集まり、チャット欄には質問や共感の声が絶えませんでした。

1. イベントの背景と目的
情報があふれる時代にあっても、「届かない情報」がある。見えていない人、聞こえていない人、読めない人……そんな人たちにどう情報を届けるか。本イベントでは、日米の文化や法律、技術や現場の視点を交えながら、“届く社会”をどう作るかを考えました。
伊藤さんは冒頭で「情報に飢えていた感覚」を共有。字幕や手話があってもニュアンスのズレや抜けがある体験を語り、「だからこそ技術と人の工夫で壁を越えたい」と熱く語りました。
2. 日米の違いから見えるアクセシビリティの課題
maddyさんは「アメリカでは法律や訴訟リスクが背景にあり、“義務”としての強さがある。一方、日本では“思いやり”の文化が入り口になることが多い」と話します。どちらにも強みがあるが、日本では“必要な人がいない前提”になりがちな点を伊藤さんが指摘。「毎回『必要です』と言わなければならない負担がある」と実体験を語りました。
参加者からも「手話や字幕が“特別なもの”扱いされている」「事前申請がハードルになっている」という声が上がり、チャットでも共感の嵐。アクセシビリティを“声を上げなくても届く仕組み”にする重要性が共有されました。
3. 企業・組織へのアプローチ
「企業の価値観を理解して、アクセシビリティをその価値に結び付けることが大切」とmaddyさん。株主や経営層には“数字”が効果的であるとも。障害者や高齢者の人口データ、機能利用率など具体的な数字を提示することで納得感を得やすいそうです。伊藤さんも「法律やガイドラインだけでなく、現場で役立つ運用を一緒に考えるのが重要」と補足しました。
例えば、「株主にどう伝えるか」という質問に対して、maddyさんは「影響度を数字で示すことが一番響く。例えば“スマホのアクセシビリティ機能を使っている人が何%いるか”を伝えるだけで、経営層の目が変わる」と具体例を挙げました。
4. 技術と人の両輪
maddyさんは祖父母がろう者であり、またエンジニアとして訴訟対応をきっかけにアクセシビリティを意識したエピソードを披露。「本来、インターネットは壁をなくす道具のはずが、新たな壁を作ってしまうこともある」と感じたそうです。さらに、子どもの頃に祖父母と連絡を取るためにTTYというキーボード付きの機器を使い、ゆっくり文字を打ちながら会話していた体験を紹介。「今ならビデオ通話やスマホで手話も使えたのにと思うと、当時の制約を強く感じる」と振り返りました。
伊藤さんも「技術の進歩は頼もしいけれど、人の理解やサポートが不可欠」と強調。手話や字幕があっても誤訳やニュアンスのずれが起きる。特に字幕精度の工夫として、「字幕があっても専門用語が多いと理解が難しい。だからこそ要約やチャプター表示、手話との併用など複数の工夫が必要」と具体例を示しました。チャット欄では参加者からも共感の声や「自分も家族との連絡で苦労した」などの体験談が寄せられました。
5. 「道を増やす」情報設計
イベント後半では、「バリアフリー」という言葉への違和感も話題に。「道を壊すのではなく、道を増やすほうが前向き」と伊藤さん。手話、字幕、やさしい日本語、イラストや要約など“複数の道”を用意することで、誰もが選べる社会に。maddyさんも、自身の選挙体験で「やさしい日本語のサイトに救われた」と振り返り、「多様な前提に開かれた設計が必要」と賛同しました。
また「当事者が毎回申告しなくてもよい世界」にするために、アライ(支援者)の存在も重要であるとの指摘も。「誰かが代わりに声を上げてくれるだけで負担が減る」との発言に、多くの“いいね”がつきました。
6. 質疑応答のハイライト
参加者からは実践的な質問が多く寄せられました。
- 自治体勤務者:「意識が低い職場では何から始めれば?」→「SNSやメディアをうまく使って関心を集める」「小さな改善を積み重ねる」などのアドバイス。例えば“市役所の案内図を改善してメディアに取り上げてもらった例”も共有されました。
- 選択肢を広げるには? →「やさしい日本語、手話、多言語化など工夫を」「セルフアドボカシーの支援も大切」。例として“イベント参加フォームに手話・字幕・音声ガイドの選択肢を追加した事例”も紹介されました。
- ライブ配信の注意点 →「誰が話しているか明記」「話す速度や間を意識」「字幕・通訳への配慮」。実際のZoom配信では“発話者名を画面に表示”など簡単な工夫が効果的とのコメントも。
- 非エンジニアでもできること →「PDFが読み上げられるか聞いてみる」「小さな気づきをチームに共有するだけでも大きな変化に繋がる」。ある参加者は「Slackに『この資料、読み上げ対応してますか?』と聞いたらチーム全員が考えるきっかけになった」と体験談を語りました。
7. まとめとこれから
「アクセシビリティは特別な人のための話ではない」「誰もが情報を選び取れる社会にするための工夫」。そんなメッセージが印象的な夜となりました。伊藤さんは「情報の壁は1人では壊せないが、隣に誰かいれば大きな穴を開けられる」と締めくくりました。
最後に、登壇者2人からの嬉しいお知らせも。「実は、情報アクセシビリティについての共著を執筆中です。完成を楽しみにしていてください!」とのこと。チャット欄でも「絶対読みたい」「楽しみ!」と盛り上がりました。
読者への呼びかけ:
もしこのレポートを読んで「自分にも何かできるかも」と思ったら、まずは身近な資料やサイトを確認してみませんか?「この情報は誰に届いているのか」「届いていない人はいないか」をチームで話してみる。それだけで社会を少しやさしくする第一歩になるかもしれません。
(文責:NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長 伊藤 芳浩)