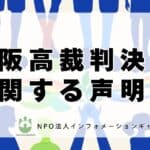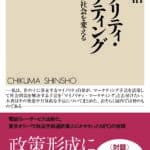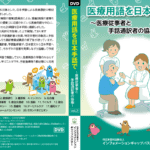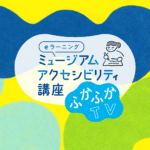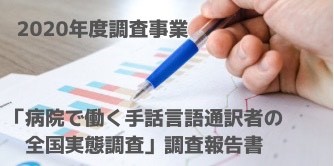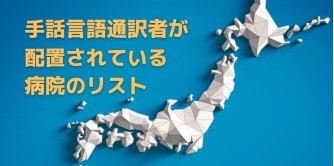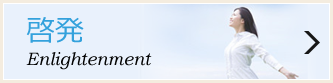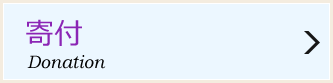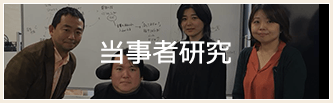【ご報告】内閣府への合理的配慮啓発動画に対する要望提出
2025年11月20日(木)に、NPO法人インフォメーションギャップバスター(IGB)は、内閣府が運営する YouTube チャンネルに掲載されている啓発動画「合理的配慮の提供~アニメでわかる障害者差別解消法~」(2022/04/28公開)を対象に、改善を要望する文書を提出しました。その際、内閣府政策統括官(共生・共助担当)付参事官(障害者施策担当)古屋 勝史様、および同参事官補佐 平野 忠様との意見交換の場を設けていただき、直接手交と対話による議論を行いました。

古屋参事官(障害者施策担当:右)と意見交換する伊藤IGB理事長(左)
【提出の背景】
動画は、聴覚障害者に対する「合理的配慮」の内容を紹介する公式コンテンツとして位置づけられています。しかしながら、現状では「手話通訳が難しい場合に筆談で対応する」という事例にのみ焦点が置かれており、制度として整備されている「手話通訳・要約筆記」を利用できる選択肢が視聴者に提示されていないという課題を、私たちは指摘しました。このままでは、視聴者が「筆談で十分」と誤認し、支援制度の認知を妨げるおそれがあると考えたため、今回の要望書提出に至りました。
【意見交換の要点】
1. 古屋参事官からのご説明
-
当該動画は3年以上前に制作されたもので、現在の状況と合致しない部分がある
-
制作当時は当事者の参画が十分でなかったため、ろう者から見て不自然なところもあると思う。今後もし動画を作り直す際には、当事者にも入っていただき、一緒に作っていく形を検討したい
-
手話・文字化アプリ・遠隔通訳など、利用可能な手段は多様で、より深い内容にできる可能性あり
-
一方で、他障害とのバランス、動画の尺、制作体制・予算という制約あり
これらを踏まえ、今後の改善に向けて、ご意見をうかがいながら丁寧に検討を進めたいとのお話がありました。
2. IGBからお伝えした主なポイント
聴覚障害者のコミュニケーション手段は多様であり、「筆談で十分」という一律の紹介は実態と乖離してしまうこと
- 聴覚障害者のコミュニケーション手段は 手話・筆談・文字支援・口話など多様であり、「筆談で十分」と示す構成は実態を反映しない
- 手話は 独立した言語であり、日本語字幕や筆談の代替ではないため、動画では 手話通訳の選択肢を明確に伝える必要がある
- 国の公式動画は事業者・自治体・一般市民に強い影響力をもつため、一つのコミュニケーション手段のみを描く構成は誤解を生み、支援の質に波及するおそれがある
- ICT手段(遠隔通訳・文字化アプリ)は有効であるが、高齢者や地域差により利用困難なケースもあるため、あくまで選択肢の一つとして提示すべきである
- 複数の支援方法を提示することで、「当事者が自分に適した手段を選べる社会」を示す啓発になる
- 今後の見直しにおいては、当事者との協働を前提に制作することが不可欠であるという点を改めて強調

古屋参事官(障害者施策担当)に要望書を手交する伊藤IGB理事長
動画というメディアは、社会の共通理解を形成する強い力を持っています。私たちは、制度として手話通訳・要約筆記が整備されているという事実を、映像の中で明示することが、共生社会の実現に向けて重要であると考えています。今後とも、当事者の視点を踏まえた建設的な対話を重ね、障害者差別解消法の理念「共生社会」を一層推進してまいります。